|
昨年秋の文学フリマ、当日僕は残念ながら参加できず(ご挨拶できなかった皆様すみません)、久湊に頼んで買ってきてもらったのが、このZINE『朝になっちゃうね』です。 初谷むいさんによる文――口語短歌のようでも、自由律詩のようでもある言葉と、 横井もも代さんによるデザイン――夜明けに羽ばたく鳥のようにも、バスタブに浮かぶ花びらのようにも見える幾何学模様の装丁とが、夢幻的な美しさをみせる一冊です。 ――いや、これでは何も言っていないのと同じことですね。 「なんだかよくわからないけど良い」という陳腐な感想を書くことは憚られたものの、僕自身まだこの本のことをよく掴み切れていません。だからこそ、あえて記事にしてみようと思います。 正体を見極めるために書く、という怠惰な書評にもいくばくかの価値を見出してくれる読者の寛大さを信じて。 書名についてまずはこのなんとも秀逸なタイトルについて。 この『朝になっちゃうね』には、「#01 それからのわたしたちのその途方もなさ」という副題がついています。 おそらくここに短歌の詩型意識があることは間違いないでしょう。 どういうことか。歌人の山田航さんの言葉を参照してみます。 「短歌4拍子説」というものが現代ではかなり浸透しており、短歌は厳密に言えば5・7・5・7・7ではなく4拍5小節のリズム内なら何をやってもいい詩型であると捉えたうえで作られている短歌が現代にはたくさんある。 補足すると、短歌には5・7・5・7・7の韻律の原則からあえて外れる「句またがり」という技法がありますから、それを用いて、五小節のなかで(ときにはそこからも外れながら)自由に詠むことが可能になっているということでしょう。 仮にこの本のタイトルを定型どおりに切ってみると、 (5音)あさになっ となり、初句と二句、四句と結句のあいだで文節が句を「またがって」いることが分かります。 (※短歌では撥音「っ」は1音とし、拗音「ゃ、ゅ、ょ」は音に数えません) なお、いま僕は二句の音数を揃えるために、本の号数表記と思われる「#01」に無理やり「ぜろいち」という音をあてています。そうすることによってなじみ深い三十一文字の詩型を回復できますし、「ぜろに」や「ぜろさん」を予感させることで、「朝になっちゃうね」という台詞に続くいくつものパラレルワールドの存在を示すこともできる。 しかし、ひょっとするとここではあえて「読まない」という勇気が求められているのかもしれません。どういうことか。 あさになっちゃうね/◯◯◯◯/それからの/わたしたちの/そのとほうもなさ ◯◯◯◯は四拍分の休符だと思ってください。 「朝になっちゃうね」と呟いたあとの沈黙、無言の「間」がそこにあるのです。 場末のホテルに泊まって、夜通し起きていたふたりが、白み始めた窓の外をみてふと「朝になっちゃうね」とつぶやく。徹夜してしまった重たい頭で、新しく始まろうとしている一日のことを考えて、とほうもなくなる。 音響工学では、無音の部屋でマイクを用いて録音したときの「サーッ」という音を「ホワイトノイズ」と呼ぶそうですが、まさにこの「間」はそれに等しい、無言の音声的表現なのです。これは定型詩でなければできないことです。決められた五七五七七という韻律があってはじめて可聴化されるギャップなのですから。 そしてこの休符(全休符)を挟むことによって、詩は現代短歌における五小節の原則をも維持しえています。なんと周到で緻密な、そして洗練された表現であることでしょう。 大胆、さらに大胆、そしてつねに大胆。山田氏は、以下のように述べて、初谷さんの作風が現代短歌における「リズム感覚の革命」であると評しています。 「短歌4拍子説」を歌人たちが内面化したのは西洋音楽の感覚が日本中に行き届くようになってからだろう。(中略)しかし西洋音楽のリズム感を身につけて4拍子を使いこなしてきた現代歌人たちですら、「休符」をうまく使いこなすことはこれまでなかなか出来ていなかった。初谷むいは「休符」の力を使いこなそうとする新しいリズム感に挑戦しており、そしてそのベースになっているのは現代のポップ・ミュージックのセンスではないかと思われる ポップ・ミュージックのセンス、というのが何のことを指すのか、僕にはまだ理解できていませんが、たとえばポップ音楽の大部分は、4拍子かつ「8ないし4小節」をひとまとまりとして作曲されていますから、「朝になっちゃうね」において、二句目がまるっと落ちて「4小節」に接近していることもまた必然なのかもしれません。 とはいえ、ここで注意しなければならないのは、この無言の「間」=「途方もなさそのもの」ではないということです。もしそうだとすると、 朝になっちゃうね/◯◯◯◯(=途方もなさ)/それからの/わたしたちの/その途方もなさ と、二重に「途方もなさ」について詠み込んでいることになってしまう。ですから、この「間」というのは、あくまで「次第に明るくなってゆく窓をふたりが眺める」時間でなければならない。途方もなさはその後にやってくる感情です。 換言すれば、作者はここで巧みに休符(=書かないこと)を用いてみせていますが、しかし鍵となる心理、すなわち「途方もなさ」については、はっきりと言葉にしているということです。「書かないことで書く」というようないたずらに敗北主義的な破調ではなく、あくまで「書く」、すなわち言語への透徹した意識があることを忘れてはいけないように思います。 有色雑音ところで、ホワイトノイズ、と書いたのには、もうひとつ理由があります。 それは横井もも代さんによる装丁の素晴らしさを伝えるため。 この本の表紙は、幾何学模様の印刷された紙のうえに、大きさの異なる半透明の紙が重なるつくりになっています。トレーシングペーパー的なアレです。 このトレーシングペーパー的なアレをパタパタ開いたり閉じたりすると、背景の模様がぼんやり浮かんできたり、消えたりするのですが、これがなんとも美しい。少しだけ開けられた窓のむこうに、早朝の街の色づかいが見えてくるようです――夜明け前のひときわ暗い空のような濃紺と、今はまだ地平線のむこうで準備されている朝陽のようなローズピンク、そして無機質なコンクリートを思わせるグレー。夢見るような曲線によって描かれたビフォア・ドーンの世界です。 だとするならば、このうっすらと白い半透明紙は、そんな夜明けの窓のこちらがわに広がる親密な世界――「朝になっちゃうね」を包み込む沈黙――の卓抜な表現とみることができるでしょう。 そして、そこに書かれたタイトルロゴもまた、よくできています。大きさの不揃いな、すこし傾いたレトロな書体は、無邪気で楽しげなようにも、追憶のせつなさを宿しているようにも見えます。気心の知れた友達どうしのじゃれあうような「朝になっちゃうね」なのか、これで最後と決めた夜をすごす恋人たちの「朝になっちゃうね」なのか……そうして訪れるいくつもの「途方もなさ」に思いを馳せることは、まったく幸せな読書というほかありません。 血と涙さて、内容の分析に入りましょう。
しかし、どのような切り口で書いたものでしょうか。だいたいが短詩型文学というものは、語られるものよりも、余情として示されるものの方が必然的に多くなるわけですから、評者の側にも肉を斬らせて骨を断つようなきびしい覚悟と選択がなければなりません。 だとするならば……初谷むいという歌人の言語操作における洗練については上でひとまず論証しえたものとして、次はその目指すものについて考えてみるのがよいかもしれません。
0 コメント
(※あまりにも長くなってしまったので、記事を上下に分けて公開することにしました。サークル「本質的にちくらぎ」さんの『あみめでぃあ Vol.6』に関するレビューは(上)を御覧ください。) 一方で、つれづれ推進委員会さんもまた「創造と概念の新しい関係」をモットーに掲げておられます。もともとはバンドとして活動しておられたという三人組で、今回は作品を購入すると、小説(文庫本)と楽曲(オンライン配信)の両方を楽しむことができます。 ということで、今は楽曲版『うみべの出来事』を聴きながらこの文章を書いているのですが、「楽曲を文学フリマで頒布する」=「文学としての音楽」というのはなかなか興味深いコンセプトだと思いました。というのも、言語芸術としての文学は積極的にせよ消極的にせよ概念を扱わずにはいられないわけですが、メロディーやハーモニーやリズムからなる音楽経験には「概念」のように明晰に言語化された思考が介在する余地があまりないように思われるからです(あまり、と書いたのは絶対音感のことが念頭にあったからです。すべての可聴振動を十二平均律として聴く、というのは概念的把握に該当するような気もしますが、当事者でないこともあってよくわかりません)。 とはいっても、もはやベートーヴェンの生涯をフリードリヒ・フォン・シラーの詩から切り離して論じることはできないでしょうし、文人音楽家というにはあまりにも文学者でありすぎたリヒャルト・ワーグナーらのロマン派歌劇や、ジョン・ケージのような実験的試みまで、文学(ないし哲学)と音楽はつねによき伴走者であり続けてきました。またポピュラー・ミュージックにおける歌詞の重要性は言うまでもありません。 ではいったい、音楽にのせて歌詞が歌われることを、われわれはどのように理解するべきなのでしょう?それは感官による概念的思考の侵蝕なのか、あるいは概念による世界の調教なのか、それとも理性と情念の実存における再統合なのか?そもそも言語の起源とはなんなのか、概念をもちいた抽象的議論と心情のこもった歌唱の違いとは……?僕にもまだ上手く答えられませんが、まただからこそ、単なる”文学性”から一歩踏み込んで「概念」に焦点を定めたつれづれ委員会さんの試みはとても興味深いものに思われてきます。 小説版『うみべの出来事』についても見てみましょう。本作には「存在について」というサブタイトルが付せられています。高校生活を舞台に、他者のまなざしによって安心と不安のあいだを揺れ動く自己のありかた=「存在」を、光と影とに仮託しながら描いてゆく――まさに青春小説の佳作といっていいでしょう。物語が進むにしたがって欠けていたピースが嵌ってゆく(「謎解き」に近い)構成になっているので、ここではあまり内容については書きませんが、あえて主体をぼかした語りの効果だったり、場面転換のそつの無さであったりと、技術的な良さも多い作品だと思いました。 著者の吉岡大地さんは『あとがき』で、物語を書き進めるにつれて作中人物たちの新しい一面が見えてきた、という趣旨のことを書いておられます。多くの小説家が吉岡さんと同じように、執筆中に「登場人物が生きて、勝手に行動しはじめる」という境地のことを記していますが、概念の集合(=設定)でしかなかった人物が、活き活きとした生として、いわば「存在感」を持ちはじめるという現象もまた、ひとつの面白いテーマだなと思います。 年歩むさて、いよいよ2017年も終わりを迎えようとしています。 色々と考えながら書いているため時間がかかっていますが、今後も折をみてレビューは続けてゆきたいと思います。 もちろん創作も。 すっかり堪能したので、今年はここまで。 それではごきげんよう。皆様よいお年をお迎えください。 石田幸丸(習作派編集部)
年の瀬せまる12月、皆様いかがお過ごしでしょうか。 去る11月23日に、習作派は第二十五回文学フリマ東京に参加してきました。 『筆の海』を買っていただいたり、また他サークルさんの雑誌に触れたりするなかで、いろいろと考えたこともあるので、書き留めておこうと思います。 まずは購入した雑誌のレビューから。第一回はこれまでとちょっと毛色の違うものを。 ふたつ隣のブースで出店されていた、ばあらさんの作品です。 『三重吉さんてこんな人 1』 『三重吉さんてこんな人 2』 『松根東洋城てこんな人』 『鈴木三重吉ゆかりの地めぐりin広島』 『三重吉さんてこんな人』毛色が違うといったものの、これぞ文フリ、という作品だと思います。 漱石門下のひとりで児童文学者としても知られた鈴木三重吉について紹介したマンガです。 三重吉の生い立ちや性格、交友関係などを簡単なストーリー形式で追ってゆくのですが、たいへん面白く読みました。一巻は三重吉出生から最初の自著刊行まで、二巻は生涯にわたる友人たちとの交流を主に扱っています。また、無料配布ということで、三重吉の親友松根東洋城をメインに据えたスピンオフ作品『松根東洋城てこんな人』と、文学碑や墓所についての紀行マンガ『鈴木三重吉ゆかりの地めぐりin広島』もいただきました。 考えてみれば、歴史上の人物について研究するというのはいかにも不思議なことですね。見たことも会ったこともないひとりの人間について思いを馳せ、残された文章や写真からその生について再構成してゆく。今を生きる他人のことすら(あるいは自分自身のことすら)完全には理解できないのが人間なのに、あえて時間のへだたりを超えて誰かの内面に迫ろうというのですから。 饒舌な余白かくいう僕(石田)もまた、大学院ではジャン=ジャック・ルソーという思想家について研究していました。どちらかといえばより思想・哲学的な側面からのアプローチだったので、ルソーの為人についてあまり触れることはなかったのですが、それでもルソーは研究対象である以前に心の友でした(もっとも、現実のルソーはかなりつきあい難いタイプだったようですが)。それは、僕が抱える、この世界についての根源的な問いを、きっとルソーも共有してくれているのだという確信からでした。 本作において、ばあら氏は当時のテクストや三重吉自身の書簡などに丁寧にあたっておられ、おそらく国文学研究の正道を踏まえた上での創作なのだと思います。しかしながら、あるいはだからこそ、その描き方にはやっぱり、たんなるコミカライズ以上のもの、作者個人の「根源的な問い」としか言いようのないものが反映されているように思いました。三重吉と森田草平とのあたたかく血の通った友情を描く氏の筆致が、きわめて印象的で胸を打つものだったからです。 小宮(豊隆)は君に書け書けと云って迫る相だ。迫る人も一人は無くちやならぬ、僕は待つ人に成ろう。君が書くまでまたう。書かないで――書くことを忘れて、それで尚ほ生きて居られる人間ではないと三重吉を信ずるから僕はあわてない。(『三重吉さんてこんな人 2』森田草平から鈴木三重吉への書簡より) 寛大というか悠長というか、まあなんとものんびりして気の長い話ですが、僕自身同人誌を作ってみて、なんとなく共感するところもあります。 そこにあるのは、たとえば(再会の約束を果たすために生命を擲ち生霊となって駆けつけるという)『雨月物語』のような苛烈で自己犠牲的な信義とは別の、もっとしなやかな紐帯です。同じ目標へと向かって歩む、あるいは歩んでいると信ずる者たちだけのあいだに生まれる静謐な信頼。言語をあやつるメチエによって藝術家たらんとする文学者たちの、その友情や愛情が、むしろ非言語的に成立していることの――まさしく友情の〈行間〉の――美しさをこそ、作者は描きたかったのではないか。(もっとも、読者ないし編集者としては「書け」と迫ることこそ愛情でしょうから、その点で小宮豊隆もちゃんと親友としての面目を施しているとせねばなりませんね) 金曜日のモナミ三重吉の友人で、自身も俳人であった松根東洋城が、寺田寅彦と待ち合わせて連句をつくる物語も素敵です。 『金曜日のモナミ』と題されたこのスピンオフ・エピソードにおいて、東洋城は待ち合わせ場所である新宿の喫茶レストラン「モナミ」にふらりとやってくる。そうして寅彦とふたり食事をしながら取り留めのない話をして、一段落したところでようやく連句にとりかかる。店内のざわめきは背景へと遠ざかり、静思沈吟するふたりの時間はゆっくりと過ぎてゆきます。 ややあって閉会となり、店外に出たときにはもうすっかり夜の帳が降りていた。夜道にふたりは「また来週」「うん、またね」とだけ言い交わして別れる――たったこれだけの淡然たるエピソードですが、やはりそこには語られる以上の信頼と知的な安らぎがあって、あたたかい余韻を引くのです。どちらかがモナミに現れない日が続いても、きっと先でまた会は開かれ続いてゆくのだろうと思わせるような……。ちなみに「モナミ」とはフランス語のmon ami、すなわち「私の友人」という意味ですが、なかなか素敵なタイトルだと思いませんか。 藝術家どうしの、あるいは人と人のあいだの無時間的な交感というのはそれ自体ひとつの興味深いテーマです。それは『菊花の約』における左門と宗右衛門の交情が時間的制約によって際立たせられるのとは意味深い対照をなしている。後者が生の帰趨すべき「答」において相通じそれに殉じたとすれば、前者は永遠にひらかれた「問い」を手形として時の関門を踏み越える、と言ってしまっては牽強付会でしょうか。書き続ける/読み続けるということは、すべての古人が同時代人のように慕わしく、すべての同時代人が古人のように常しなえの存在であると感じられるような、そんな境地に遊ぶことなのかもしれません。 ……などと書いてきましたが、しゃちょこばって読まずとも、本作はひとつの伝記マンガとしてじゅうぶんに楽しめるものであることは間違いありません。なんといっても絵のクオリティが高い。コマ割りや吹き出しなんかも読みやすく、プロはだし、というよりこれは完全に商業作品として成立する水準なのでは……と思わされます。そういうところもまた、文フリの奥深さですね。 すっかり堪能したので、今日はここまで。 それではごきげんよう。 石田幸丸(習作派編集部)
|



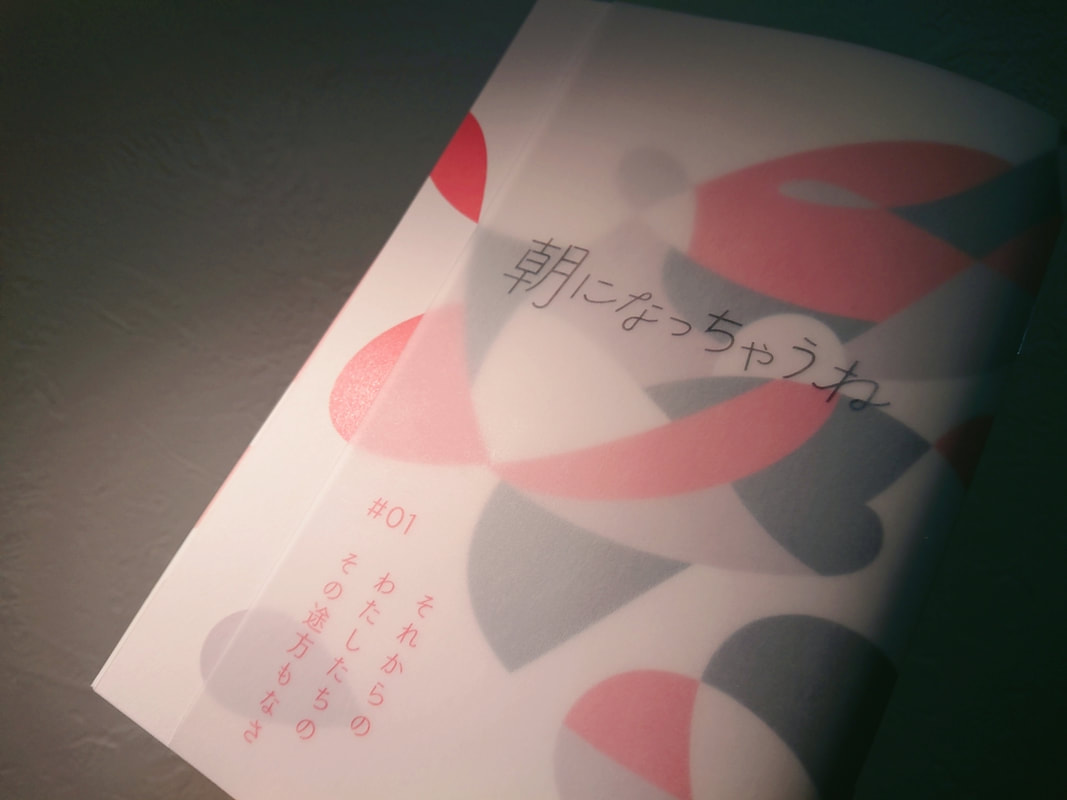
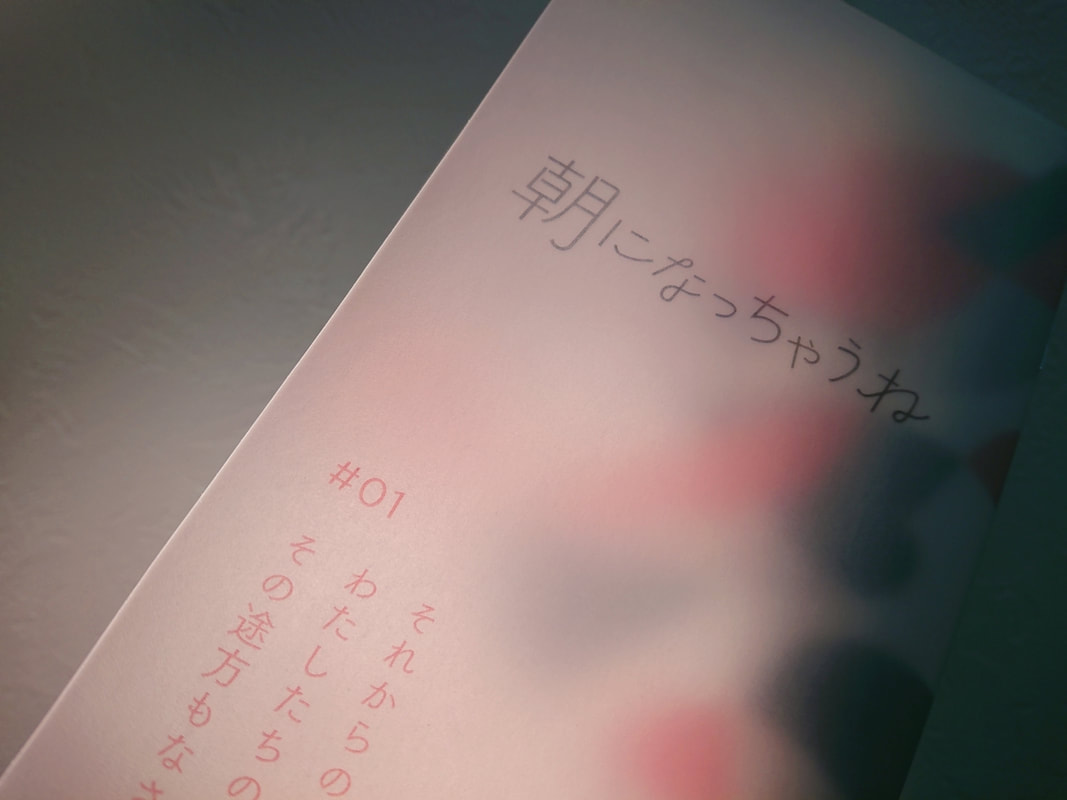


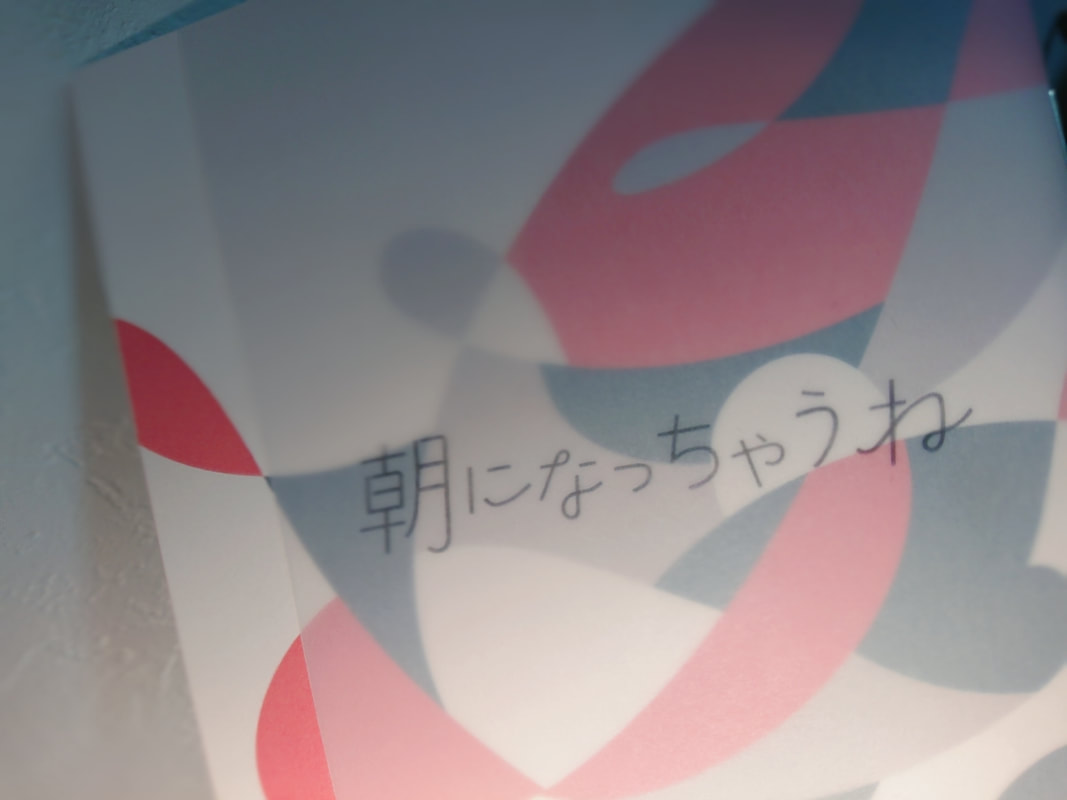
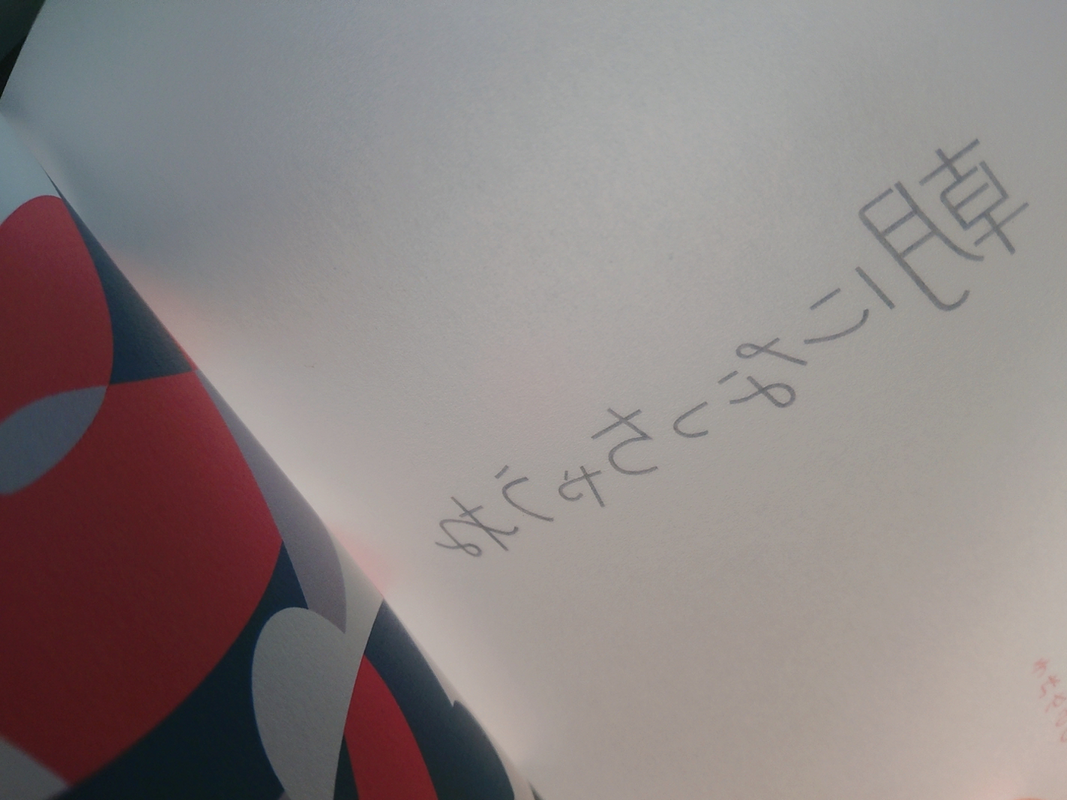

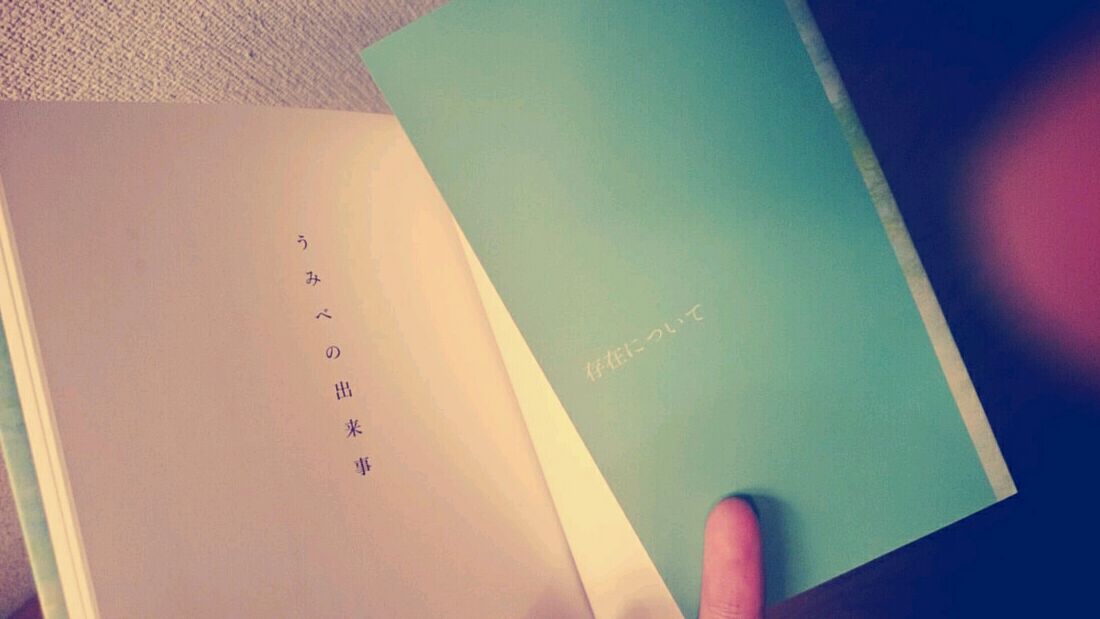



 RSSフィード
RSSフィード
