|
昨年十一月二十三日、文学フリマ東京に参加してきました。わたし(石田)が東京でブースに立つのは3年ぶり。懐かしい顔ぶれやはじめての皆様にお会いできたことは嬉しい限りです。那智さんも当日、習作派のブースにお越しくださいました。自分たちの本に興味をもってくださった方が、どのような文章を書いておいでなのかということはどうしても気になるもので、半ばせがむような形で“売っていただいた”のがこちらの一冊でした。
ほんとうは年内に公開するつもりで記事を準備していたのですが、小説としての強度がきわめて高く、またそれゆえに、わたしはこの作品と真剣に対峙することで色々なことを考えさせられたので、ずいぶん時間がかかってしまいました。書評というよりは読書メモといった方がふさわしいかもしれませんが、その記録を書いておこうと思います。 ※以下、ネタバレを含みます。 『青の痕』(那智)
『青の痕』——ここで描かれるのは、高校で英語を教える「俺」と、ひとりの男子生徒「風見」との交感です。
とある進学高で英語を教える「俺」は、生徒たちから慕われながらも、静かな孤独のうちに日々を過ごしている。ある日、「俺」はひょんなことから自身の身体に残る“傷跡”を、教え子のひとりである風見に見られてしまう。ふだんは衣服で隠している“傷跡”——それはかつて親から虐待を受けたときのもので、その悪夢は今なお「俺」を苛んでいた。いっぽう風見もまた、親からネグレクトを受けていた。ふたりの関係は特別な親密さを帯び始める。誰もいない家に帰ることを拒み、「俺」に抱いてほしいと求める風見。愛情への飢えとも、年齢相応な性的好奇心ともつかないその求めに溺れかける「俺」……。 大切なものを欠いたまま大人になった「俺」と、永遠に欠いたまま大人になろうとしている「風見」……ふたりの切なくもエロティックな行き連れは、文庫判にして五十頁に満たない掌編でありながら、鮮烈な印象を与えるものでした。 この小説を特徴づけるのは、きわめて理性的で抑制のきいたその文体です。”BL”で”R-18”という、ある意味ではかなり様式性の高いジャンルを志向しながらも、その冷静な語り口はひろく多様な読者を獲得しうると思います。 「冷静」とはどういうことか?本作において作者は「教師―生徒の性愛」というタブーの「侵犯」と、それを成立させる事情についての「エクスキューズ」を巧みに配置することで、ブレーキとアクセルを踏み分けながら坂を昇り詰めるような効果を描出しています(※)。侵犯者の心理を描くときには、罪を犯さずにはいられないという意識と、それを回避しようとする良心との両面に踏み込むことでリアリティが生じるわけですが、とりわけこの作者は行為と事情との、《罪》と《良心》とのバランスを量るのがとても上手だということです。 ※註:このように書くと、多くの読者諸氏はG.バタイユの理論を想起されるかもしれません。しかしバタイユのエロティシズム論をここに引用することには慎重にならなければなりません。バタイユは、死すべき孤独な存在としての人間が、自身の非連続性(個体性)を超出して連続性へと至る運動としてエロティシズムを考えました。その過程において、主体の非連続性を条件づけているさまざまな「禁止」は、主体そのものによって「侵犯」される。つまり、「自分を自分たらしめているルール」を破ることにエロティシズムの核心があるとバタイユは考えた。 しかし本作において、主体ははじめから登場しません。「俺」も「風見」も、その成長過程において必要なケアを受けず過ごしたために、独立した主体としての自己を確立できていないからです。作者の言葉を借りれば、ふたりはあくまで「欠けている大人」と「17歳」でしかないのです(p.50『あとがき』より)。したがってここでの「侵犯」とは、バタイユのいうそれとは区別して考えています。 たとえば以下のくだり。 ねだられるままキスをした。雨に湿った髪を撫でて、簡単に火照る首筋に触れて、拙く求めてくる舌を何度もなだめた。教室では呼ばない名前を一度だけ呼んだ。すがりつく体はいつも小さく震えていた。(p.16)
「俺」と風見とが車内で唇を重ねる生々しいシーンですが、きわめて緻密な計算が働いていることもわかります。各文のレベルで分析してみましょう。
①「ねだられるままキスをした」 まず、冒頭の一文について。衝動的なことのはじまりを表す端的な一文ですが、あくまでキス=「侵犯」は風見から「ねだられた」というエクスキューズが付されています。 無論ここで「エクスキューズ」といっても、それは本質的な弁解を意味するわけではありません。現実には成人が性的同意能力のない未成年と肉体関係をもつことは罪とされていますし、そのことは「俺」もまた承知している。そうではなく、あくまで「俺」の心理における罪悪感の一時的な緩和として「エクスキューズ」が機能しているということです。 ②「雨に湿った髪を撫でて」 ここでは風見というキャラクターの背景が示されています。本作において、風見が内的に欠落を抱えた少年であることは、「傘を差さずに雨に濡れる」という一種の自傷的行為が繰り返し描かれることで強調されてきました。そうした風見の危うさが、この車内においては大人である「俺」によって受け止められる。性愛の文脈を取り払って読めば、それはほんらい、傷つき不安定な子どもを前にした「大人として当然の」まったく「倫理的な」振る舞いのはずでした。しかし「俺」もまた暴力のサバイバーとして決定的な欠落を抱えながら生きているがゆえに、ほかならぬこの抱擁こそが堕罪への“躓きの石”となる。 このように、傷つき求め合う者どうしのシンパシーが日常的倫理とのあいだに取り持つ緊張関係こそ、まさしく本書のテーマなのであり、「俺」と「風見」の孤独として作中幾度も変奏されます。 生まれた瞬間から当然与えられるべきあらゆるものを、持たないままで育つ子どもがいる。抱擁の温度を知らないまま、静かに損なわれ続ける子供が。(p.17)
繰り返される独白はどれも切実なものであり、「俺」と風見が成年—未成年という関係に留まらず、教師—生徒という二重のタブーを破っているという現実を際立たせています。
③「簡単に火照る首筋に触れて」、④「拙く求めてくる舌を何度もなだめた」 つづく二文も同様の構造を持っています。身体的接触という「侵犯」がなされながらも、風見が「俺」の愛撫に敏感に反応し、あるいは自分から積極的に”求めて”いるというエクスキューズがなされる。重要なことなので繰り返しますが、ここでいう「エクスキューズ」というのは本質的な免罪ではなく、主人公にとって行為への没入をいざなう装置であるということです。 ⑤「教室では呼ばない名前を一度だけ呼んだ」 一方、これは決定的な「侵犯」というべきでしょう。わたしの読み落としでなければ、風見に対して「俺」の衝動がなんらかの形で「結実」するのは、作中でこの文章ただ一度きり。じつは本作において、キスやペッティングまでは描かれるものの、セックス(性器の挿入)はありません。偽善的なルールであると知りながら、「俺」が自らにペニスの使用を禁じているからです。従って、どれほど衝動が高ぶろうとも、最終的に「俺」自身が一般的な意味でのオーガズム(=射精)に達することはない。 だからこそ車内で抱き合い、風見の名前を口にするこの一瞬は、疑似的でつつましいオーガズム体験として、唯一「俺」自身の「侵犯」を示す根拠となる。 じっさい、抱擁のさなかに「名を呼ばわる」とき、そこではオーガズムによく似た自我の溶解dissolutionないし溶出élutionが経験されているように思われます。古今「名」はその人自身と紐づいたものとして呪術や宗教的秘儀(戒名や洗礼名など)の対象となってきましたが、意識が逆光のなかで震えるあの瞬間、無限に落ち続けていくようなあの感覚のなかで、他者の名前というのは唯一のよすがとなる。 しかし、にもかかわらず、作者は風見のファーストネームを決して明かしません。「教室では呼ばない名前」というその特別なことばは決して読者には開示されない。いっぽう後段、風見の側が「達する」瞬間にはその様子が描かれています。 果てる瞬間、風見は小さくハルと呼んだ。
十七歳の少年が二十七歳の教師の体を求めるということと、その逆とでは、“罪”の重さは、けっして等しくない。「書かれるべき内容が書かれない」ということの裏には、こうした関係の非対称性があります。
BL文学とともに
そう考えてみると、この筆者の書き振りのなんと緻密なことでしょう。情念のもつれを描くからといって、書き手が情念に流されていてはつまらない。むしろ燃えるような絶頂においてこそ、書き手の意識はひややかに冴えて研ぎ澄まされねばならない。文学作品が、現実の社会規範をいちど俯瞰したところに打ち立てられるものだとするならば、できあいの法律も道徳も存在しない荒野に踏みとどまって、それでもなお尊いものを描くところに書き手の「倫理」はあるのでしょう。ゆえに書かれた世界に決して惑溺しない「強さ」と「冷静さ」こそ、すぐれた書き手にとって不可欠の資質となる。こうしたモラルに支えられた細部を、わたしはとても好ましく読みました。
愛への痛切な渇望を描きながらも、安っぽいセンチメンタルな描写に堕しなかったこの作者の筆力は相当なものがあると思います。誤解を恐れずに言えば、この作者にとって“BL”はもはやひとつのバックグラウンドとなっている。つまり、作者は“BL”から出発してより普遍的な文体へとたどり着いているようにみえる……というと“BL”を過小評価しているでしょうか。あるいは、こうした文体上での「かけひき」こそが“BL”文学の様式性の精髄なのかもしれません。だとすると、この作者は最良の意味での“BL”の紹介者であるといえるでしょう。いずれにせよ、多くの読者に届くべき作品だとわたしは思います。 堪能したので、今夜はここまで。 それではごきげんよう。
石田幸丸(習作派編集部)
0 コメント
実家が海の近くにあったので、今のようにマンションが乱立する前はベランダから小さく海を臨むことができました。夜になるとたまに遠くで汽笛が聞こえてきて、小さかった僕がそれを聴くのは布団の中でした。そうして眠りに落ちると僕は大きな客船に乗っていて、他に人影はなく、ただきらきらと光る海面を眺めながら僕はどこか遠い異国へと運ばれていく。そういう夢を何度か見たことを覚えています。 今思えばベランダから見えた海は貨物港で、国内線の小さい貨物船しか寄港しないし、正面にあるのは房総半島なので絶対に異国へは連れて行ってくれないんですが、子供の頃ってなんでも冒険に結びつけちゃうんですよね。まぁそんなこんなで僕は今でも海が好きで、うちの雑誌にもちゃっかり「海」が入っているんですが、とにかくそんな僕が文フリに参加する前からTwitterで気になりまくっていた同人誌を今日はご紹介したいと思います。 ※ネタバレを含む書評となりますので、未読の方は読んでからご覧いただくことをお勧めします。 ※各所引用を含んでおりますが、作品のクオリティ担保のため表紙以外の写真は使用しておりません。 ぜひ著作をご覧いただきたいと思います。 レモネード航空『貨物船で太平洋を渡る』 もう、タイトルから男の、いや漢のロマンをビシバシ感じる。 「太平洋を船で渡る」だけでもわくわくさせてくれるのに、「貨物船」です。 え?そんなこと可能なの? そして外観。 ご覧の通り背表紙にしか表題がなく、表裏の表紙には大きく写真が置かれています。 表は船体に押し寄せて弾ける白波が、裏には夕暮れの中横たわる無数のコンテナが、それぞれ写っています。確かに、これに白抜きでタイトルがあっては邪魔になってしまうかもしれません。無条件に目を引く、美しいデザインです。 そしてページを捲るとめちゃくちゃかわいいロゴが! ちなみにこれは本が入れられていた封筒にもスタンプで押されていました。 ここまでの情報で既に満足気味だった僕ですが、勢い込んで内容に入っていくとあれよあれよとページを捲ってしまい、そのまま読了してしまいました。仮にも「書評」を謳っているのでもちろん内容も触れていこうと思いますが、先に書いておきます。 この同人誌、マジでとんでもない本です。 凄まじい情報量 まず目次を見ると「はじめに」というサブタイトルが見えたので、「執筆にあたる経緯かな?」と思い隣のページに目を移したんですが、そこには夥しい量の文字情報が詰め込まれていました。 冒頭の文章を引用させていただきます。 数年前から船舶全般に対する興味が高まり、国内の長距離フェリーや海外航路を走る貨物線への乗船、小型船舶免許や関連する海上無線資格の取得などを経験しました。こうしたイベントを通じ、自身の興味が船旅から海上交通の決まり事、海運へと進んでいくことを感じていました。特にコンテナを中心とする海上流通の奥深さは私の心を掴んで離しませんでした。「何とかして、コンテナ船に乗船出来ないものだろうか。」今回はこのような興味から始まるコンテナ船乗船記です。 え? 小型船舶免許? 海上無線資格だって? 思ってもみない情報に、一瞬茫然としてしまいました。僕は何も考えずに、大型のフェリーのような貨物船が存在していて、それに数日揺られながら窓の外の写真が並んでいるような、そういう「一般的な」船旅の派生だと考えていたのです。 そこからかけ離れた《ガチ勢》感。 なんだか初っ端から申し訳ない気持ちになりました。 そして、特筆すべきは冒頭文章の情報量です。 確かに経緯であることに間違いはないんですが、この熱量、この整い方。まるで海運商社に出す志望理由書です。僕が人事だったら間違いなく採用する。面接なしで採用する。 さらに「はじめに」はこれで終わりません。その後は旅に関する厖大なデータが記述されてゆきます。 旅行概要に始まり所要日数、条件、旅行費用とその詳細な内訳、用語の解説。そしてその後第1章「旅程立案と資料請求」へと進みます。その後も必要な書類や契約すべき保険、連絡した代理店など事細かに行動が整理されて書かれており、後塵を拝す旅行者は大助かりでしょう(コンテナ船で太平洋を渡る冒険者が他にいればですが)。 冒頭の文章から先、著者の「動機」が明確に記されている部分はないに等しいのです。それはおそらく、著者にとってこのコンテナ船の旅が絶対に「必要」なものであり、実施することは前提条件かそれ以前の問題だからなのでしょう。それだけの意欲と覚悟をもって旅行を計画し、実行に移したからこそ、執筆の段階で熱量を注ぐべきは可能な限り情報を整理することだった。そんな印象を受けました。 縦書きじゃなかったら外資コンサルのリサーチレポートかと見紛うほどのクオリティだな、と考えて、あることを思い出しました。 お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、先ほどの表紙の写真、波の写っている方が表です。ということは右開き、つまり縦書きで書かれているんですね。 こういった写真が多く挿入された大判の冊子って、個人的には美術リーフレットとかカタログのように左開きであることが多いように感じます。現にこの本を手に取った時、僕は最初裏から開いてしまいました(そしたらとんでもない量の参考文献が出てきました)。 しかしこの本は縦書き。文中には英文や数値など横書きの方が簡便なものも多いにもかかわらず、です。 僕はこの、一定の難読性を孕んでも縦書き表記を選んだ部分に、「これは旅行文学なのだ」という矜持めいたものをこの時感じました。読み終えた今となっては、これは半ば確信に変わっています。 出だしからスリル溢れる展開 情報の小波をかき分けてしばらく進んでいくと、あたかも湾内から沖合に出てうねりに飲まれるように、いくつものトラブルが著者(主人公)を襲います。関係各所との書類やメールのやり取り、難航する手続きの数々は、並の旅行者なら逃げ帰ってしまうようなものばかりです。しかし著者はそれらをユーモラスな描写や色合い豊かな数々で彩ることで、読み応えのある、テンポの良い文章としてあらわしています。 例えば、横浜の旅行代理店の店員らが「コンテナ船旅行者」という前代未聞の処理を迫られ混乱している様を見た著者の、 「しまった、息をするようにご迷惑をおかけしてしまっている。」 といったセリフであったり、 やっと辿り着いた乗船地ブリスベンにて、いざ船旅のスタートを切ろうとした矢先、 コンテナ船に備え付けられた鉄製の長い階段を登ると、保安担当の方に声を掛けられます。 と言うクスッとしてしまうような描写があったり。 こう言った文に釣られるようなかたちで、段々と自分も一緒になって旅をしているような気分が込み上げてきます。ユーモアとスリルのバランスが見事な、流れるような文章運びです。 いざ、横浜へいよいよ乗船。見開きで夜の帷の中に浮かび上がる巨大なコンテナ船が現れ、次ページから船旅が始まります。 目指すは日本、横浜。そう、これは「日本に帰る物語」なのです。 文章は沖合から外洋へと滑り出してゆき、波は静かに読者の周りを取り囲んでいるかのようです。進むごとに変化する空や雲の様子、船内の様子や船員との会話が淡々と連ねられています。 ユーモアが散りばめられた文体はそのままに、文章の表情は穏やかなものとなっていきます。船内の設備や食事の様子は写真とともに詳しく語られ、著者の感想や独特の視線と共に非常に面白く描かれています。まさに旅行記という雰囲気が好奇心を唆り、ページを繰る手が止まりません。 ゆったりと静かな情景が続き、ありふれた異国の紀行を見ている気分になっていると、唐突に海の恐ろしさが立ち現れます。途中の避難訓練(Drill)のシーンなどは「そうか、船は穴が空いたら沈むんだな」という当たり前のことを無造作に突きつけてきて、ぐっと作品のリアリティを引き上げていると言えるでしょう。 文章もさる事ながら、写真の美しさが作品の魅力を何倍にも引き上げています。錆び付いた甲板、油の匂いが漂ってくるかのような機械の数々。前半とは打って変わって色彩が抑えられた写真の連続は、もしかしたら表紙から裏表紙にかけての色調のグラデーションを成しているのかもしれません。それは著者(主人公)の心境、目線の変化を導いているようにも見ることができます。 旅の終わり あっという間に、本当にあっという間に、船は横浜に着いてしまいます。 無事に着いてほっと胸を撫で下ろすと同時に、もうこの旅が終わってしまう喪失感、もっと一緒に旅をしていたいという無闇な欲求が読者を満たします。 最終ページ。表紙の写真、コンテナ船上部から見下ろすアングルが、コンクリートの埠頭へ着岸したことを示すために再度使われています。見事な対比によって寂寥感がさらに強くなります。 退船前に船員の一人との会話。彼はまだ数回、同じ航路を往復することになることが明かされます。彼の旅はまだ終わらない。一緒に連れて行ってくれ、と僕は叫びたくなるも、中盤の「海の恐ろしさ」が思い出され、言葉に詰まる。そんな複雑でもどかしい気持ちになり、単調に行われる帰国手続きの文章を目で追うしかありません。 そして、そんな感情のまま、物語は幕となります。 「冒険」の経年変化冒頭でも書いた通り、僕は今でも海が好きです。幼少期に思い描いた船旅を、いつか実現したいと密かに思い続けいた自分を、今や認めるほかありません。 しかし、当時思い描いていた異国への船旅は、その先の土地、つまり、穏やかな田園風景であったり、宗教建築物の群れだったり、荒涼とした砂漠や茹だるような雨林、雄大な山々、はたまた瞳や髪の色様々な人でごった返す市場のような、そういった写真や映像で見る異国の面影と地続きだったように感じます。 この本の船旅は、そういう我々が思う旅の醍醐味のようなものを提示してはくれません。むしろ対照的な、なんというか、非常に個人的で、慎ましい、錆や油と潮風の匂いをもたらすに留まっています。 ですが、わくわくします。言葉で表せないほど好奇心を刺激してくれる。 それはもしかしたら、僕がもう大人だからなのかもしれません。子供の頃に憧れた旅は、飛行機や車を使ってもうあらかた見た景色でできています。行ったことのないグランドキャニオンも、なんなら行く術のない火星の景色だって、グーグルマップで見ることができます。そうした情報の断片から、その土地の風景を想像することを続けた結果、いつしか本当に驚き、ときめいて、感動するようなことがなくなっていたのではないでしょうか。 経験値のない子供の頃、毎日は冒険の連続でした。 じゃあ、大人になった僕たちの冒険って何なのでしょうか。色々見て知って、想像してきてしまった僕たちがまだ知らない景色。それを、本書は見せてくれているのだと、僕は思います。 著者は冒頭で本書を「コンテナ船乗船記」としています。ですが、僕にとってはこの本は「冒険小説」だったようです。昔読んだ『エルマーの冒険』や『宝島』のような、わくわくさせてくれる冒険譚。色合いは変わっても、抑えられないほど心が揺らされてしまうこの感覚は、まさしく冒険のそれなのです。『貨物船で太平洋を渡る』は、間違いなく僕の人生をレモネードのような爽やかさで、豊かにしてくれたと思います。 余談ですが、このクオリティで著者は1人、文フリのブースも単独でいらっしゃいました。校正者にご家族の方らしき名前が見受けられるものの、ほぼ全ての作業をお一人でされているようです。凄まじいセンスと努力を感じます。 また、同人誌作成のステップについて、noteやTwitter(@lemonade_air)で詳細に語られています。作成の動機や目標、こだわったポイントなど、こちらも丁寧にまとまっていて読み応えのある記事です。 (参照リンク:【旅行記同人誌を作成した話】) ご購入がまだの方、もしいらっしゃいましたら、リンク先の取り扱い書店一覧をぜひチェックしてください。 この本は、しばらく本棚の一番目立つところに収まると思います。ふとした時、手にとって眺めたい作品。そういうものを僕たち習作派も作っていきたいものです。 長々書いてしまいましたが、本当に面白い文章でした。田巻さんのこれからにも大いに注目したいと思います。 それでは、夜も更けてきたのでこの辺で。 久湊有起(習作派編集部)
月並みですが、早いもんで12月ですね。 いよいよ迫る年波に対抗するべく(?)地元ヤンキーがよく着てる「着る毛布」ってやつを買ってみましたが、確かにあったかいものの顔と手先だけはどうしようもなく冷えるので、結局ファンヒーターを解禁しました。ヤンキーもなかなか苦労しているようです。 少し間が空いてしまいましたが、第4回目はラドン「上陸」レビューです。 装丁
|


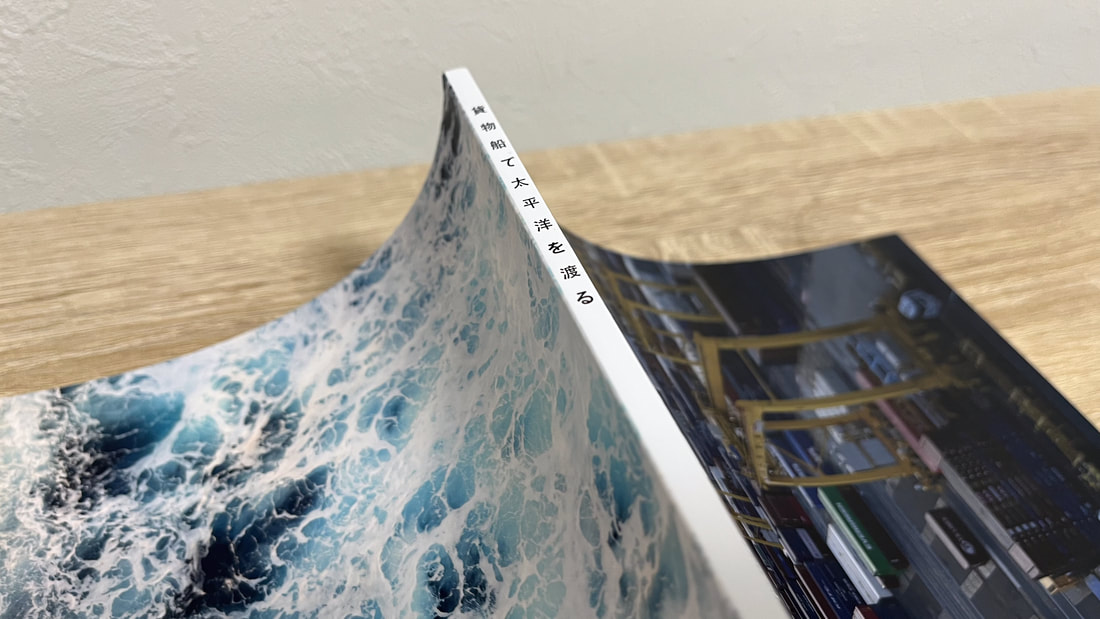


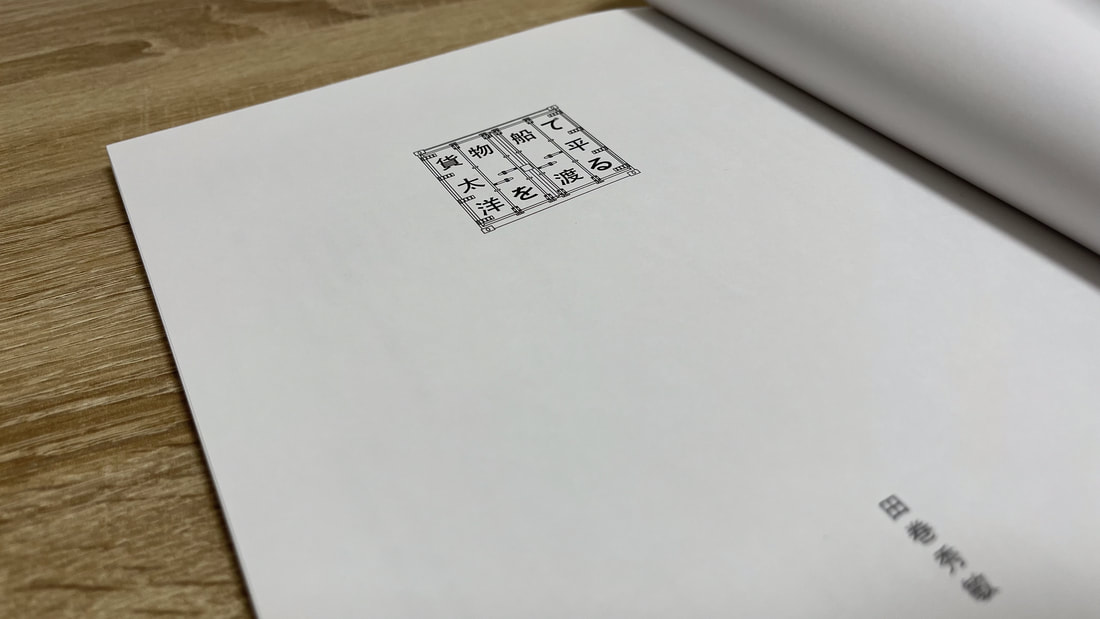




 RSSフィード
RSSフィード
